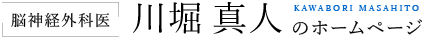くも膜下出血後の微小血管SpasmにはNETsが関係している
Perivascular Neutrophil Extracellular Traps Exacerbate Microvasospasm After Experimental Subarachnoid Hemorrhage
Ryota Nakagawa; et al
Stroke. 2024 Dec;55(12):2872-2881.
<Abstract>
くも膜下出血(SAH)後の遅発性脳虚血には微小血管攣縮(スパズム)が関係していて、その原因は炎症と言われているが詳細は不明であった。今回動物モデルにおいて出血早期に血管周囲に現れる血小板がDAMPsとして引き金となり、出血後2日以内に好中球が集積しNETsを形成する事が分かった。NETsを抑制するとスパズムも減少し、治療ターゲットとなりうる事が分かった。
<Figures>
Illustrative figure
くも膜下出血によって本来血液の無い血管周囲に血液(特に血小板)が集積する。その刺激(DAMPs)によって好中球が血管内から血管外に遊走してきて、NETsを作って血管壁のSpasmを起こす。DNaseを用いてNETsを減らすとspasmも減る
 出血から30分で血管(緑)周囲に血小板(赤)が集積している。5日後にはスパズムが生じている
出血から30分で血管(緑)周囲に血小板(赤)が集積している。5日後にはスパズムが生じている
出血直後に血小板(緑)が血管(青)の外側に集まっているが、翌日から翌々日には好中球(赤)が大量に血管外に進出している

<Introduction>
くも膜下出血において大きい血管の攣縮(スパズム)はクラゾセンタンで防ぐことが可能だが、近年では小さい血管のスパズムへの対応が重要であると考えられてきている。そこで今回二光子顕微鏡を用いて微小血管のスパズムに対して好中球細胞外トラップ(NETs)がどのように関与しているかを調べた
<Method>
miceに脳槽血液注射法でSAHを作成し、二光子顕微鏡を使用して血管(Dextran)、血小板(PE/FITC-抗血小板抗体)、好中球(LysM-EGFP)、NETs(Cytox green)を可視化してスパズムの変化を測定した。そのうえで、好中球の除去(anti-Ly6G抗体)やNETsの除去(DNase-1)を行い、スパズムへの影響を見た
<Result>
血液挿入後、数秒で血管外腔に血小板が大量に蓄積し、2日で消失した(ビデオ有り)が、5日後には血管のスパズムを生じていた。好中球は翌日には浸潤してきてNETsを形成した。好中球もしくはNETsの形成を阻害するとスパズムおよび脳血流が改善した。
<川堀の感想>
くも膜下出血翌日には好中球が浸潤し、NETsを血管外で形成して、スパズムを誘発する事を可視化で来た素晴らしい論文。我々もNETsに着目しており、この制御は脳のダメージを減少させると信じている。ただ、この論文は起きている現象について精査したものであり、それのみでは患者の改善につながらない。このモデルを用いて、どの様な薬剤等がSpasmを抑える事が出来るのかについて次の研究が求められる。